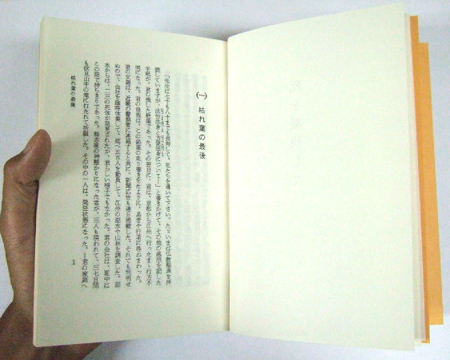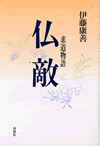| HOME > 本・DVDのページ > 死を凝視して | |
死を凝視して |
|
|
|
||||||||||
| 書 名 |
死を凝視して 売り切れました |
|||||||||
|
|
||||||||||
| 発 行 | 華光会 | |||||||||
|
|
||||||||||
| 価 格 | 800円 (送料210円) | |||||||||
|
|
||||||||||
| 案 内 |
伊藤先生の指導により獲信した若者の求道記録。刻々と迫る死を凝視して、ある者は不治の病に対する生の執着に泣きながら、血みどろの求道の末に死を超克した真実の記録。とりわけ、死の直前まで綴られた『死の日記』は鬼気せまり、『最後の手紙』の叫びには胸打たれる。
|
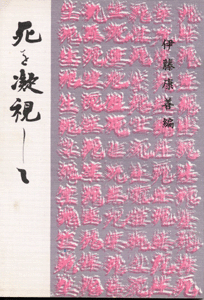 |
||||||||
|
|
||||||||||
| 著者/編者 | 伊藤康善 編
|
|||||||||
|
|
||||||||||
(本文より) |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
目 次 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
| レビュー(感想) |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
関連情報 「伊藤康善師の法話音声」 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
関連書籍・新刊 |
|
|
|
|
||||||
|
『突然、皆の沈黙を破った坊さんが軽く手を挙げて、すみの方に寝ている・・・ 』 |
『サブタイトル〜蓮如上人の御教化〜 表題のほか、『決定のこころ』『蓮如上人の教化の根源』『五重の義と信心往生』・・・
』 |
『親鸞聖人の深い感動をうたった『三帖和讃』を学ぶためにこれ以上はない、最強のテキストが登場!著者の18年にわたる・・・ 』 |
『大好評の上巻(「浄土和讃」「高僧和讃」)に続き、待望の下巻(正像末和讃)が、ついに完成・・・ 』 |
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
『たいていの者ならば、ここまで進むと愛想をつかして、腹を立てて二度と来ない・・・ 』 |
『一ツトセ |
『戦争に電撃戦あり、長期戦ある如く、求道に頓機あり又漸機あり、・・・ 』
|
『アフリカの砂漠で、千古の沈黙を守るスフィンクスは、われわれに謎の質問を・・・ 』 |
|||||||
|
|
||||||||||
立ち読み・試聴ページ |
|
|
 なむあみだぶつのこころ (DVD) 増井悟朗 |
 じょうどへのあゆみ (DVD) 増井悟朗 |
||||||
|
『では、私が先に申しました、「生きた人の葬式」とは、どんなことか・・・』 |
『ひとりの旅人が、西に向かって歩きつづけていました。だれ一人いない広々とした・・・』 |
「お念仏ってなに?お葬式のためのもの?」といった、初めての方にもわかりやすく・・・
|
増井悟朗師が自らの求道と伝道の歩みをふりかえります。悟朗師の・・・ |
|||||||
|
|
 求道の急所 華光会 編 |
 冥加について 増井悟朗 |
|
|
||||||
|
『信心決定病
いつか私は、信心決定病という言葉を使ったことがあります。これは・・・』 →つづきはこちら |
『真宗の求道の急所の一つは、「後生の一大事」とふみ出すことである・・・』
|
『いのちがあるから、眠くなったり、しんどくなったり、また元気になったりする。体だけ・・・』 |
増井悟朗氏らの法話、また質疑応答を通して、浄土真宗のお話を分かりやすく・・・ →★つづきはこちら
|
|
||||||
立ち読み・試聴ページ |
|
 ほとけさまのプレゼント(DVD) 増井裕子 イラスト・声 |
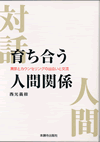 育ち合う人間関係 西光義敞 |
|
|
|||||
|
『妙好人生産事業 その鈴木大拙さんが、晩年に及んで浄土真宗の妙好人・・・』 →つづきはこちら |
ほとけさまのプレゼント、それはお念仏の教えです。
浄土真宗の入門編・・・ →★試聴ページはこちら |
真宗からカウンセリングへ。カウンセリングから真宗への深い提言。特に、実践に裏付けられた・・・ → つづきはこちらら |
『浄土真宗は親鸞聖人からはじまった宗派であることは、たいていの人が知っていることでしょう。けれども・・・』 →つづきはこちら |
『決定的だったのは、在家のお婆さんが伊藤康善先生にちらっと言われたという言葉でした・・・』 →つづきはこちら |
||||||
 仏教とカウンセリング (入門 真宗カウンセリング2) 西光義敞 |
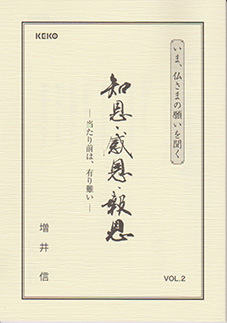 知恩・感恩・報恩 増井 信 |
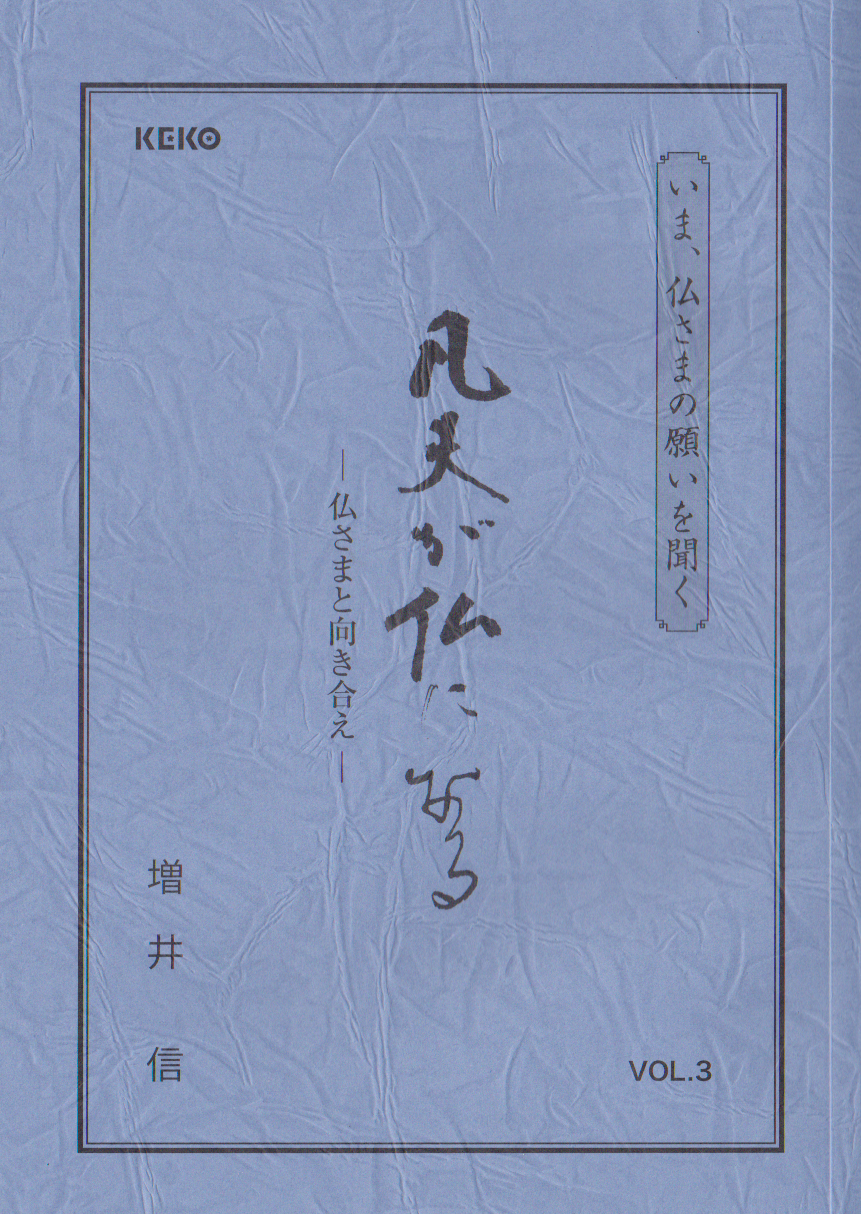 凡夫が仏になる 増井 信 |
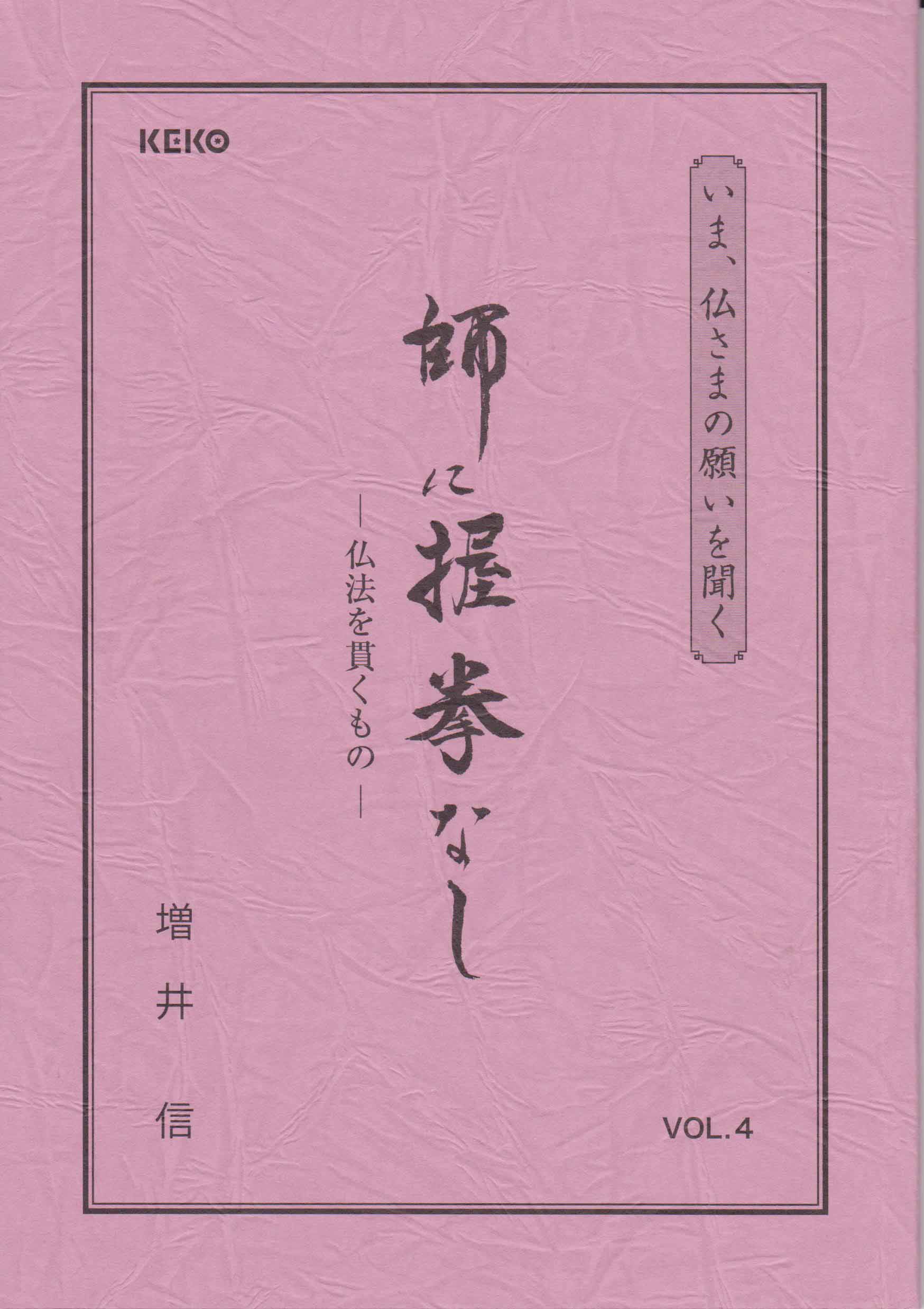 師に握拳なし 増井 信 |
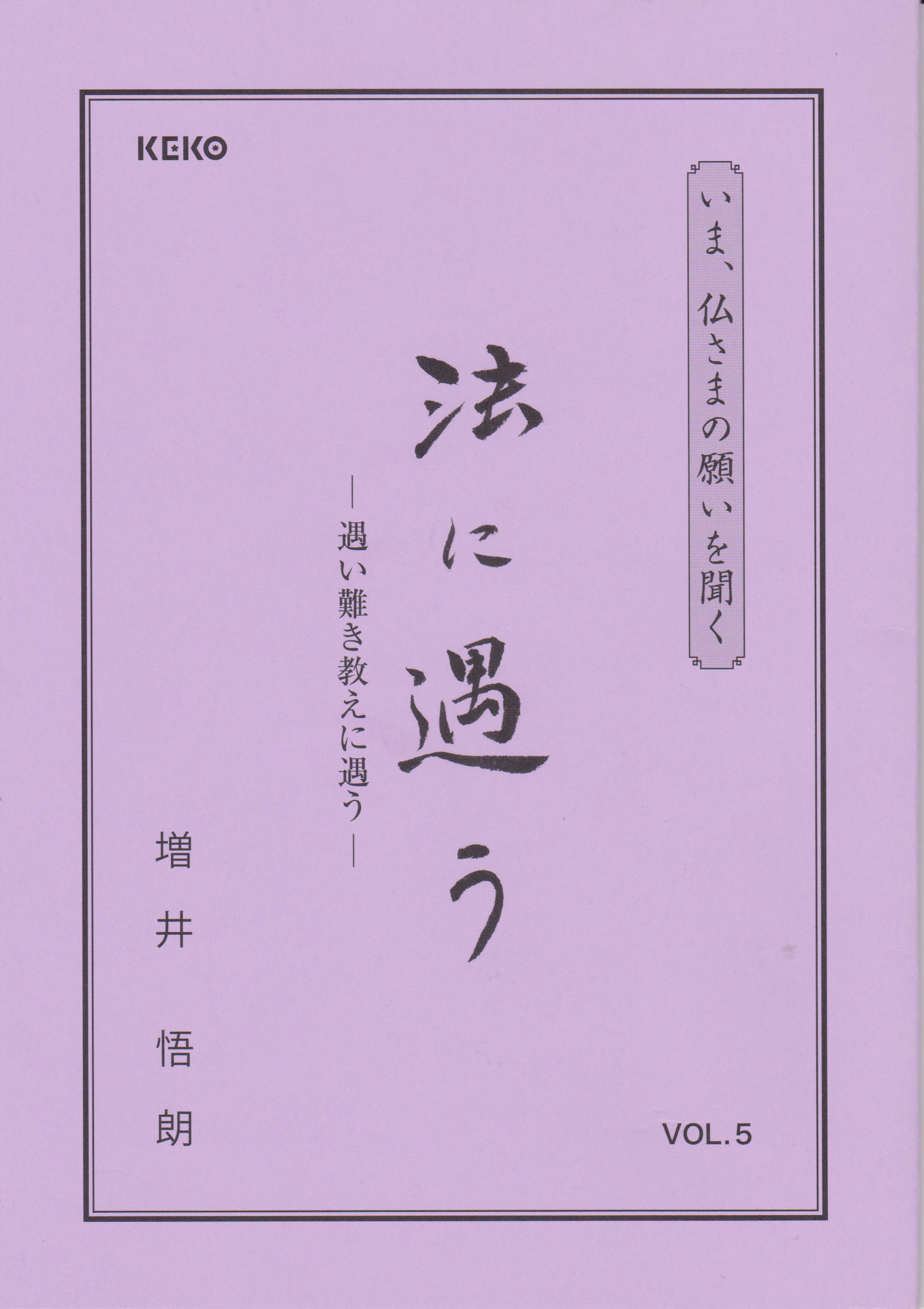 法に遇う 増井 悟朗
|
||||||
|
札幌での「西光先生を囲む研修会」の記録第2集です・・・ →つづきはこちら |
増井信師小冊子第二弾! →つづきはこちら |
増井信師小冊子第三弾! →つづきはこちら |
増井信師小冊子第四弾! →つづきはこちら |
増井悟朗師小冊子 →つづきはこちら |
||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
※平日の10:30〜18:00はお電話でもご注文いただけます→華光会事務局:075−691−5241 |
||||||||||